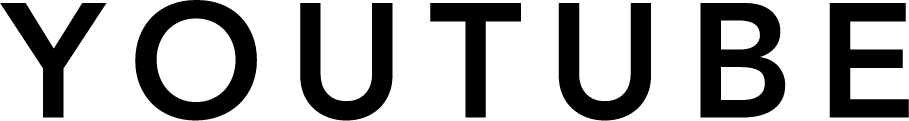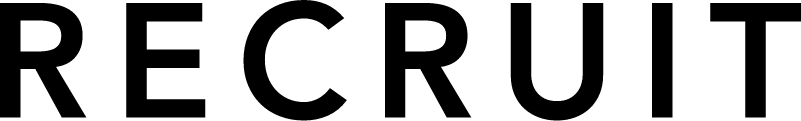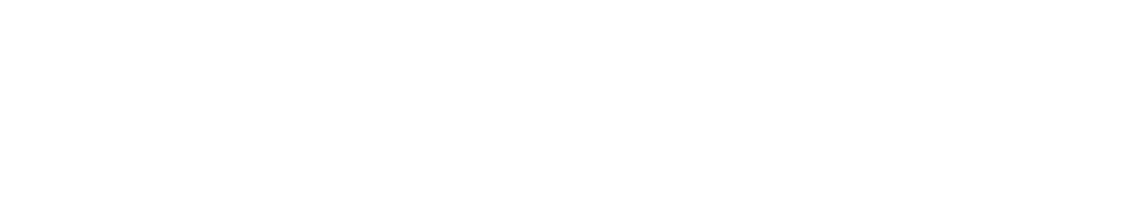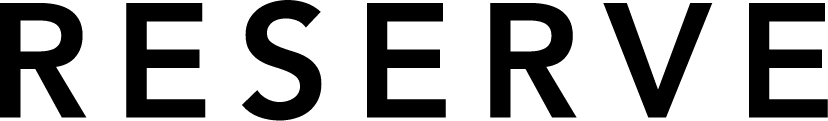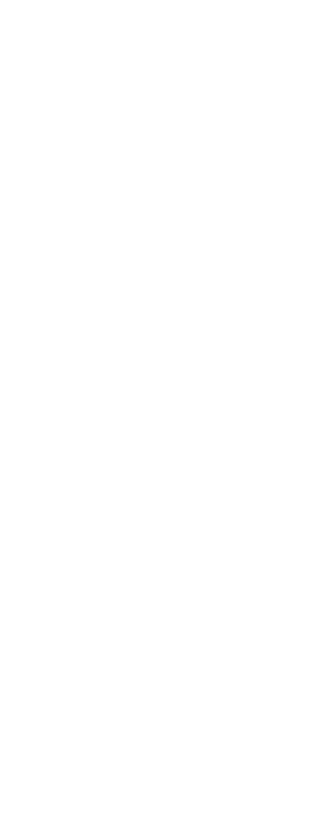FOOD
読みものとしてのスパイスカレー
学生の頃。
毎週のように通っていたカレー屋さんがあった。
雑居ビルの二階にひっそりと佇む、
ほんの10坪にもみたないような本格インドカリーのお店。
インド人によく似た痩せっぽちのマスターが
25年間ひとりで営業しているお店。
看板も出ておらず、通りにも面してないため、
前を通り過ぎる人たちは店の存在に気づかない。
だけど、いつ訪れてもびっくりするほど満席だった。
コンクリートの壁には、段ボールの切れ端に
黒の油性ペンで書かれたメニューが無造作に貼られていて
メニューはカレー、チャイ、バナナケーキの3つだけ。
そのどれもが目が飛び出しそうなほど美味しくて
私はインドに行った気分で、スパイスカリーを堪能した。
二階から通りの景色が見渡せる窓際の席が、
私のお気に入りだ。
各席には無地のノートが置いてあって、
訪れた人たちが思い思いに好きなことを書いている。
私もお店に訪れた際はそのノートに
今の自分を綴ったりした。
その日あった良いことや悪いこと。
淡い恋心や進路のこと。
どうにもならない悩みや感情。
知らない誰かが「かわいいね」なんて
コメントを書き残してくれたのを見つけては
ちょっとときめいたりもした。
社会人になって忙しくなっても、
休みの日はマスターのカレーを食べにいった。
そのころになると、マスターとも
話をすることがふえていた。
私がマスターのカレーがどれだけ美味しいかとか
覚えたてのスパイスの話をすると
マスターは目尻の皺を深くしながら
嬉しそうに笑ってくれる。
マスターの笑いかたは大口を開けて笑わない。
口元にそっと優しい笑みを浮かべるだけ。
それがなんとなく仏様の像と被って
もしカレーの神様がいるならば
マスターみたいなんじゃないかとおもった。
マスターのカレーを食べてから、
私はスパイスカレーの虜になる。
マニアックなスパイスショップを
行ったり来たりしながら、夜な夜なスパイスを
調合しながらカレーを作る。
「いつかマスターのカレーと同じくらい
美味しいカレーを作るんだ」
マスターにそう宣言すると、マスターはその時だけは
大口を開けて楽しそうに笑ってくれるのだった。
そしてそれが、マスターとの最後の会話になった。
*
それからすぐあと私は職場結婚をし、子供ができた。
慣れない育児の繰り返しの日々に
いつのまにかスパイスカレーをつくることも
なくなっていく。
マスターのカレーを思い出すことはあったけど
だんだんとお店にも行かなくなった。
そうこうしてるうちに、私たち家族は
別の町に引っ越すことになる。
それからは、もう本当にいろんなことがあった。
飛び上がるくらい嬉しいことも。
死にたくなるくらい悲しいことも。
いろんな荷物を抱えて、元いた町に戻ってきた時には
最後にマスターのお店を訪れてから
もう何年も経っていた。
(マスターのカレーが食べたい)
唐突に思い立って、電車を乗り継ぎ
何年かぶりにマスターの店に向かった。
だけど、マスターの店はどこにも見当たらない。
(間違っているはずはない。何年も通ったお店だもん)
そう思いながらあたりを探すけど
見覚えのある、あの雑居ビルはどこにもないのだ。
完全に竜宮城から戻ってきた浦島太郎状態で、
私は途方に暮れた。
後になってわかったことは、私が引っ越した二年後
マスターはインドに帰ったということだ。
(やっぱりマスターはインド人だったのか)
いや、もしかしてインド人によく似た
ジャパニーズじゃなくて
ジャパニーズによく似たインド人だったかもしれない。
そんなことをあれこれ考えても、
わかっていることはただひとつ。
もうマスターのカレーが食べれないということだ。
(こんなことなら、引っ越す前に
マスターに会いにいけばよかった)
ドアを開けたときに漂うクミンシードの香りと
マスターの笑顔が脳裏をかすめて、悲しくなった。
*
新しい職場の近くには
シェフ御用達のスパイスショップがあった。
なんとなく訪れてみると、懐かしいスパイスの香りが
鼻をつく。
スターアニスにターメリック、
コリアンダーにクミンシード。
懐かしさに胸をときめかせてスパイスに手を伸ばす。
「いつかマスターのカレーと同じくらい、
美味しいカレーをつくるんだ」
そう宣言した時の、マスターの楽しそうな
笑顔を思い出す。
(マスターのカレーと同じくらい
美味しいカレーが食べたい)
何種類ものスパイスをカゴに放り込み、レジに向かう。
キッチンに立ち、フライパンに多目の油をひいて
クミンシードとたまねぎを炒める。
マスターの店のドアを開けたときの懐かしい匂い。
「おかえり」と、カレーの神様が微笑んだ匂い。
アメ色になっていくたまねぎを見つめる。
トマトの水分を飛ばす。
鶏肉をヨーグルトごと加えてみる。
「インドみたいな匂いがする」
インドに行ったことのない10歳の娘が
隣の部屋から顔を出す。
バターを溶かしてガラムマサラをテンパリングしてみる。
味見をしてみるけど、
やっぱりマスターのカレーとはちょっと違う。
そんなことを休日のたびに繰り返す。
「おうちの中の匂いがインドみたいになってきたね」
インドに行ったことのない6歳の息子が言う。
もう一度味見をしてみるけれど、
マスターのカレーとはやっぱり違う。
ほんとうは、マスターのカレーの味も
だんだんおぼろげになってきている。
悲しいかな。人間の記憶は良いことも悪いことも
忘れるようにできている。
でもはっきり覚えてるのは、ひとくち食べた時の
飛び上がりそうな美味しさと仏のようなマスターの笑顔。
それを頼りに今日もスパイスを重ねる。
鍋の中で、時間とともに深まっていくカレーの色。
「美味しい!」
ひとくち味見をした娘が目を細めて声をあげる。
「なんかいつものカレーとちがう」
ひとくち味見をした息子が目を細めて渋い声をだす。
そんな二人を横目で見ながら、ふと幸せな気持ちになる。
キッチンいっぱいにふくらむスパイスの香り。
マスターのカレーと同じくらい美味しいカレーが
ほんとうにできたら、マスターはびっくりするかな。
またあの時みたいに、楽しそうに
大口で笑ってくれるだろうか。
ちょっとだけ切なくて、でもワクワクしながら
そんなことを考える。
鍋の中でマスターによく似たカレーの神様が
微笑んだ気がした。